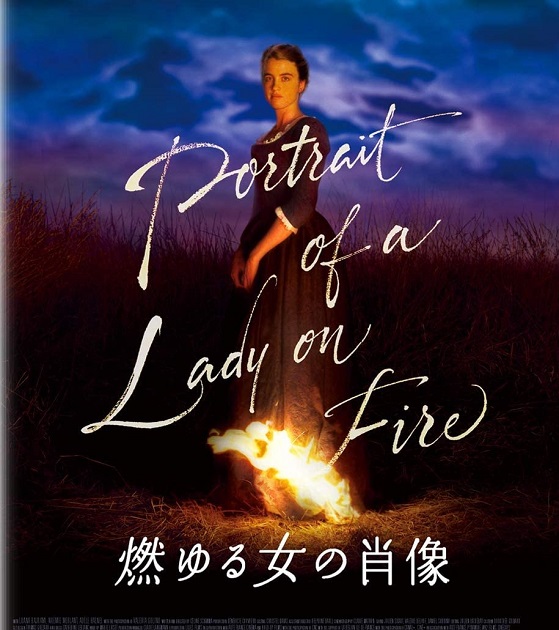
女性しか登場しない舞台設定のなかで、
徹底した女性目線で丹念に紡がれる燃ゆる恋
映画の紹介
18世紀末のフランスの孤島を舞台に、望まない結婚を控えた女性と、その女性の肖像画を描くために雇われてきた画家の女性とが、生涯でたった一度の恋に落ちる。結婚においても職業においても圧倒的な男性優位の社会にありながら、女性同士が互いの知性と感性を認め合い、共感に満ちた時間を熱く、静かに交換しあう。「こんなロマンスをこそ待ち望んでいた」と言いたくなるような、我が愛着の一本。
原題: Portrait of a Lady on Fire
制作:2019年 フランス
脚本・監督:セリーヌ・シアマ
キャスト:ノエミ・メルラン アデル・エネル ルアナ・バイラミ ヴァレリア・ゴリノ
映画の見どころ
point 1 海を越えてやってくる強き女
画家のマリアンヌが、肖像画の依頼を受けて、フランスのブルターニュの孤島に単身で海を越えてやってきます。早くもこの映画が描く女性のとんでもない意志の強さを見せつけるシーンです。マリアンヌが乗る舟には、船頭と4人の漕ぎ手がいますが、荒波に揉まれて、いまにも砕けてしまいそうなくらい頼りない小舟です。
あんのじょうマリアンヌが持ち込んできた大きな荷物――木枠で梱包された画材が波にさらわれて海に落ちてしまいます。驚いたことにマリアンヌは一瞬の躊躇もみせず、舟の男たちにいっさい頼ろうともせずに、自分で海に飛び込んで画材を舟に引き上げます。
舟が上陸すると、船乗りの一人が大荷物をかついで岩場まで運びますが、そこで荷下ろしするなり舟に引き返してしまいます。そこからは、びしょ濡れのドレスのまま、マリアンヌが自分で担いで山越えをして、目指す館まで歩いていくのです。
私はこのシーンを見ながら、「ピアノ・レッスン」の冒頭のシーンを思い出しました。主人公のエイダが、やはり荒波のなか今にも壊れそうな木造の小舟に乗って、結婚のためにニュージーランドにやってくるシーンです。舟には重いピアノが積んであり、なんとか上陸まではこぎ着けますが、迎えてくれた結婚相手の男もその使用人たちも、重いピアノを山越えさせることを拒否し、ピアノは浜辺に置き去りにされてしまうのです。
もちろんピアノと画材では重さが違いすぎます。どんなに気丈な女性でも、さすがに男たちの力を借りないかぎり、ピアノを山越えさせることができるはずもありません。それでも、私は「燃ゆる女の肖像」は、「ピアノ・レッスン」を意識してあの海のシーンと続く山越えのシーンを入れたのではないかと思うのです。
「ピアノ・レッスン」のジェーン・カンピオン監督は、女性として初めてカンヌ国際映画祭パルム・ドールを受賞しています。同じように女性たちの地位が低かった時代を背景とした映画を撮るにあたり、セリーヌ・シアマ監督はなんらかの形でカンピオン監督へのリスペクトも込めたのではないか、あるいは自分の意志を貫いて愛を選び、生き方を選んだエイダへのオマージュを込めたのではないか、そうしてエイダ以上に強く、最初から決して男たちに頼ることなく生きようとしているマリアンヌ像を描こうとしたのではないかと思えてなりません。
point 2 いよいよの、エロイーズ登場
女性画家が男名を名乗らないと仕事ができなかった時代に生きながら、自分の仕事に誇りを持ち、男に頼らず海越えだって山越えだってやってのけるマリアンヌ。演じるのはノエミ・メルラン。きりっとした黒目の眼力が印象的な女優です。ショートフィルムを監督する才女でもあるようです。
マリアンヌと恋に落ちる伯爵家の令嬢エロイーズを演じるのは、アデル・エネル。セザール賞をたてつづけに受けているフランスの実力派の女優です。このエロイーズ=アデル・エネルの登場シーンがとんでもなく印象的です。
マリアンヌがなんとか山越えして伯爵の館(別荘?)にたどりついたときにはすっかり日も暮れ、迎えは召使いのソフィだけでした。マリアンヌはソフィから、エロイーズの姉の不審死(自殺だった)のこと、前に来た画家がエロイーズの肖像を仕上げることができなかったことを聞き出します。マリアンヌが居室として案内された応接室には、その仕上げられなかった肖像画が置きっぱなしにされていました。緑色のドレスと膝の上で汲んだ両手だけが仕上げられ、顔の部分は無残に拭い取られ片鱗すらも残されていません。顔のないエロイーズの肖像画によって、そのあと登場するだろうエロイーズへの興味がいやがおうにも高められる演出です。
翌日、マリアンヌは、伯爵夫人から肖像画はエロイーズの結婚相手に送るためのものであること、ただし結婚を拒んでいるエロイーズに悟られないよう、「散歩相手」として近づき、肖像画はひそかに描くようにとの要請を受けます。
怪訝に思いながらも、プロの画家として伯爵夫人の依頼に答えるべく、応接室の片隅ににわか仕立てのアトリエを用意するマリアンヌ。そこへソフィから、エロイーズが散歩に出ようとしているという知らせが入ります。慌ててマリアンヌが階下に降りると、フード付きの青いマントを羽織ったエロイーズが背中を向けて暗い玄関ホールに立っています。そしてマリアンヌを振り切るようにさっさと扉を開けて外に出て、早足でどんどん歩き出してしまいます。
カメラはマリアンヌの目になって、エロイーズの青いマントの背中を追います。風を受けてフードが脱げると、無造作に結われた金色の髪がこぼれ出ます。やがて野原を抜け、その先に海が見えてきます。エロイーズはますます早足になり、最後には崖に向かって駆け出してしまいます。まるでマリアンヌが聞かされた、エロイーズの姉の最期を再現するように。
いまにも海に飛び込んでしまいそうになりながら、エロイーズはぴたっと立ち止まり、ここで初めてマリアンヌのほうを振り返るのです。息を切らしながら、「ずっと夢を見ていました。走ることです」と告げます。その目は、背景の少し荒れている海の色と同じように淡いブルーですが、まるで薄青い炎のような激しさを秘めています。これが、さんざん待たされたエロイーズの登場シーンです。その顔立ち、表情がやっとはじめて映し出されるところです。
思わず息をのむマリアンヌの気持ちそのままに、観客もこの瞬間、エロイーズに恋をしてしまいそうになります。
point 3 見る・見られる関係が一触即発に
マリアンヌは伯爵夫人から言われたとおり、エロイーズに身分を隠したまま、散歩の相手をしながら肖像画に着手していきます。ひたすらエロイーズの肌の色、顔の輪郭から耳の形まで、するどく盗み見てすばやくドローイングをし、それをもとにさらに記憶を頼りにしながら、キャンパスに向かって慣れた手順で描いていきます。
観察しているのはマリアンヌのはずなのですが、時折、エロイーズがあの燃えるような青い目でじっとマリアンヌのことを見返しています。エロイーズもまたマリアンヌのことをひそかに観察しているようなのです。二人はずっと「敬語」をつかって会話をします。これはエロイーズの身持ちのよさを象徴しているのでしょうが、それもあってか二人の関係はよそよそしく、なかなか打ち解けあうことができません。マリアンヌがこっそりソフィに、記憶だけでは絵が描きにくいこと、エロイーズがなかなか微笑んでくれないことをこぼすと、「お互い様では」と鋭く突っ込まれてしまいます。

それでもエロイーズは少しずつマリアンヌに心を開き、マリアンヌもなんとか絵を仕上げます。エロイーズへの淡い「友情」を意識しはじめていたマリアンヌは、母親に無理を言って自分の身分を明かすとともに、仕上げた肖像をエロイーズに見てもらいます。エロイーズはマリアンヌが自分をだましていたことに深く失望し、肖像画を見て「私はこういうふうに見えるのか」「これは私ではない」と強い調子で言い放ちます。
プロ意識を傷つけられて心外なマリアンヌは、書き上げたばかりの肖像画の顔を拭い消してしまいます。「書き直す」と言うマリアンヌに対して、母親は「書けないのなら出ていけ」と告げます。ところがここでエロイーズが「自分がポーズをとる」と言い張るのです。
晴れてマリアンヌは、堂々とエロイーズにポーズを取らせながら、集中して肖像画に臨むことができるようになります。母親から決められた期限はたった5日間ですが、館にともに残された召使いのソフィの妊娠という「事件」によって、二人の関係が急激に変化を起こしていきます。
マリアンヌはエロイーズに対して「あなたの笑顔が描けない。すぐに消えてしまうから」と言いながら、「あなたは動揺するとすぐに顔に触れる。困惑すると唇を噛む。苛立つと瞬きが減る」とこれまでの観察の成果を得意げに語ります。するとエロイーズはマリアンヌに対して「あなたが私を見ているときに、私は何をしていると?」「立場は変わらない」と言いながら「あなたは困ると額に手を触れる。怒りを感じると眉を上げる。戸惑うと口で息をする」と言い返します。
そう言われて思わず口で息をしてしまうマリアンヌを横目に、少し勝ち誇った顔で満足げなエロイーズ。二人が出会ってからずっと、肖像画を通して「見る・見られる関係」を重ねてくるなかで、お互いに気づかないままに一触即発なところまで接近していることを象徴するシーンです。
point 4 女性画家が描く肖像画のプロセス
この映画は、マリアンヌが描く肖像画のプロセスを、カンバスの下塗りの段階から、木炭によるドローイング、最後の仕上げのタッチにいたるまで、ずいぶん丹念に紹介していきます。
映画のパンフレットに掲載されていたインタビューによると、シアマ監督はこの映画をつくるにあたり、当時の女性アーティストたちのことをずいぶんと調べたそうです。18世紀後半の美術界では女性の存在感が飛躍的に増していたこと、とくに肖像画が流行したことで多くの女性が絵描きという職業に就くことができたこと、ただし彼女たちは歴史に名を残すことが許されなかったことなどを知り、興奮とともに悲しみを感じたと語っています。
その時代の女性画家といえば、マリー=アントワネットの肖像画で知られるエリザベト・ルイーズ・ヴィジェ・ルブランが有名です。日本で展覧会が開催されるほど、いまではその存在や作品が知られるようになりました。ヴィジェ・ルブランはフランス王立アカデミー会員として認められた数少ない女性の一人でした。アカデミーは毎年70人ほどの会員がいながら、女性はそのうちの4人のみと限定されていたのです。
圧倒的な男性優位社会の中で活躍の場も限られていましたが、一方で絵画やデッサンは、貴族やブルジョワの家に生まれた女性たちの「嗜み」のひとつであったとか。チャンスさえあれば、もっと多くの女性画家の作品が歴史に残されていた可能性もあったのだろうと思います。
シアマ監督はマリアンヌをそんな時代の女性画家として描くにあたり、肖像画の制作プロセスの全貌を入れたかったのだと語っています。そのため、模倣画の作家を起用するのではなく、実際のアーティストを起用することにこだわり、映画のマリアンヌと同じ三十代の現役のエレーヌ・デルメールという女性アーティストを探し当てたそうです。
エレーヌは古典的な絵画技法にも精通していたので、シアマ監督は絵画の制作のさまざまな段階を、実際にエレーヌのリアルな動作によって映し出すことができました。マリアンヌを演じたノエミ・メルランも、エレーヌのモデルを見るときの鋭い眼差しや動きを参考にし、たとえばカンバスに三歩歩み寄ってはまた三歩下がると言ったダンスのようなリズムも生かしたのだと語っています。

point 5 ソフィの選択とキッチンの友情
マリアンヌとエロイーズの関係変化は、召使いソフィも含めた女性たち三人の友情の深まりとともに描かれていきます。ソフィは、映画制作時まだ20歳そこそこの、コソボ出身のルアナ・バイラミという女優が演じています。素朴で古風な面立ちで、なんとなくフェルメールの絵に出てきそうな柔らかい雰囲気をたたえています。
母親の留守中、絵を仕上げるまでの5日の間、マリアンヌとエロイーズは、肖像画を描き散歩をする時間以外は、キッチンでソフィとともに料理をしたり、食べたり、カードゲームに興じたりします。三人は身分の違いなど意にも介さず、まったく対等に、ただし節度をもって(あいかわらずエロイーズは敬語しか話しません)友情を深めていきます。
そこへソフィの妊娠というハプニングが起こります。ソフィは迷いもせず、夫人に内緒で堕胎することを決心します。マリアンヌとエロイーズはソフィの「選択」を見守り、手伝うプロセスを経て、友情を超えた愛情をお互いに感じ合っていくようになります。
民間療法か何かにのっとって、妊娠したソフィがマリアンヌとエロイーズに立ち会ってもらいながらひたすら海岸を走り続けるシーン、草原のなか三人で薬草を探しているシーンは、女性にとっては危機的な状況のはずなのですが、なんともいえず美しく、印象深いものです。
ソフィの秘密への向き合い方で、マリアンヌとエロイーズが古い社会通念にとらわれない自由な精神をもっていること、またそのことを互いに尊重しあっていく様子も伝わってきます。そういえば、ソフィを妊娠させた相手の男が誰なのかといったことも、この映画ではいっさい話題にされません。堕胎ということへの罪の意識もいっさい描かれません。
シアマ監督は徹底して女性たちを「産む性」としてではなく、「産むことを選択する性」としてのみ描こうとしているのではないかと思います。それは、ソフィが島の女の手で堕胎に成功した夜、興奮してしまったエロイーズがソフィに協力させて堕胎のシーンをみずから演じ、それをマリアンヌに描かせるシーンにもよく現れていると思います。「産むことを選択する性」である女性は、「産まないことを選択する性」でもあるのです。
point 6 徹底して女しか出てこない映画
この映画は徹頭徹尾、女性の視点でしか物事を描きません。そもそも男性はほとんど画面に出てきませんし、出てくるとしても、冒頭の船乗りたちか、最後のマリアンヌが作品を出品した絵画展のお客さんといった「その他大勢」としてしか描かれません(あとは、ひょっとしてこれがソフィの相手かという気がしないでもない、終盤に登場して台所で食事を取る荷物配達の若者くらいです)。
その徹底ぶりは、マリアンヌとエロイーズとソフィの三人が出かける島の住人たちの「夜の集い」にも見られます。これは女だけの集いなのです。自己流の療法で堕胎に失敗したソフィは、その集いのなかで村の女に堕胎を依頼します。そのあいだ、焚き火を遠巻きにしながら、マリアンヌとエロイーズはお互いの姿を見つめ合っています。
女たちが独特のハーモニーとリズムをもった歌をうたいはじめます。美しく力強く、胸を揺さぶられる歌です。やがてマリアンヌの衣装の裾に焚き火の火が一瞬、燃え移ります。火は駆けつけた女たちによってたちまち消し止められますが、このとき明らかにマリアンヌとエロイーズはお互いの気持ちを察しあいます。
手を差し出してエロイーズを助け起こすマリアンヌのカットから、そのまま手を取り合う海の岩場の二人のカットへジャンプ、そして二人がお互いの気持ちを抑えかねて初めてキスを交すまで、急転直下にコトが進んでいきます。それまでじっくりと深度をつくりあげてきた二人の関係が一気に爆発し、燃え上がっていきます。
島の外に出れば、二人は男社会のルールに従って生きていくしかありません。ですが女だけのキッチン、女だけの家、女だけの島のなかでは、エロイーズとマリアンヌは完全に自由な魂をもつもの同士として振る舞うことができ、そのまま激しい恋に身を投じていくことになるのです。
point 7 別れを意識しながら交換する秘密
一夜をともにしたあとのマリアンヌとエロイーズの表情の変化がなんともチャーミングです。二人がベッドをともにしながら、「お互いにあのころは仏頂面で、時間をムダにしました」と交しあうシーンもありますが、気持ちを分かち合ったあとの二人は、ベッドで寝乱れた姿をお互いにさらしながら、まるで少女のようにかわいらしく、くつくつとよく笑います。

その寝乱れたベッドを傍らに、二人は肖像画を仕上げていくのです。絵を描きながらキスを交し、ベッドに入って愛を交し合っては、また絵に向き合う。母親が戻ってくるまでのわずかな数日のあいだを、かたときも離れまいとするかのようです。ですが、そんななかで、マリアンヌは白い花嫁衣装のエロイーズの幻影を見たりします。目の前に迫っている別れの時への意識がそうさせるのでしょう。
別れの意識は二人の気持ちにも波風をたたせます。もうほとんど完成しかけている絵を前に、「あなたが人のものになる(結婚する)ことを思うと、この絵も消してしまいたい」と告白するマリアンヌに、「手に入れたら私を責めるのですか」と言い返すエロイーズ。「(結婚に)抵抗してほしいなら、ほしいと言ってください」「いやです」と、この期に及んで互いの気持ちを試すような言い争いをしてしまっては、また許し合って抱き合うという激しい時間を過ごします。
いよいよ絵が完成した日の夜、二人はベッドで裸で過ごし、お互いの肖像を交換します。マリアンヌは自分のペンダントの中に、小さなエロイーズの肖像画を描きます。次に、エロイーズから懇願されて、エロイーズが片時も手離さない本(マリアンヌから借りている本なのですが)の中に、自分の肖像を描きます。裸のエロイーズの股間においた鏡に自分の裸を写しながら、描くのです。二人がわずかな日々のなかで交換した濃密な時間が忍ばれるような絵です。
point 8 オルフェとユリディスの物語
マリアンヌとエロイーズの関係を暗示する物語として、ギリシア神話のオルフェとユリディスの物語が効果的に使われています。
もとよりエロイーズは知的な女性で、結婚のために孤島の館に幽閉されてしまう前は、修道院で読書や音楽に親しみ充実した日々を送っていたようです。お祭りの夜にこっそり買ったという「媚薬」のようなものをマリアンヌに使わせるシーンもありますので、修道院の女性同士で危ない恋愛ごっこを愉しむようなおませな面ももっていたのかもしれません。
そのエロイーズがまだ仏頂面を装っていたころに、マリアンヌに乞うて借りた本がギリシア神話の本でした。エロイーズはこの本をむさぼるように読んでいたようで、ソフィと三人で過ごしているときに、オルフェとユリディスの物語を朗読して聞かせ、そのあと三人で感想を語り合うシーンがあります。
オルフェというのはアポロンから伝授された竪琴をシンボルとする吟遊詩人です。妻のユリディスが死んだとき、オルフェは冥界に下って妻を取り戻そうとします。得意の竪琴を奏でて冥界の王を説得し、なんとか妻を連れ戻そうとしますが、もう少しで冥界から抜け出すところで、王との約束を破って振り返って妻の姿を見てしまったため、妻は冥界に引き戻されてしまいます。日本のイザナミとイザナギの冥界下りそっくりな話です。
この物語について、ソフィは「振り返るなんてひどい。無意味だ」とオルフェの行為を非難し、エロイーズは「愛ゆえの行動だ」とオルフェをかばいます。マリアンヌは「オルフェは我慢するよりも、妻との思い出を選んだ。夫としてではなく詩人としてそうしたのだ」といかにもアーティストらしい見解を披露します。それに対してエロイーズは「妻のほうが、振り返って私を見て、と言ったのかもしれない」と、あくまでもロマンチストらしい考えを口にします。
このやりとりは、マリアンヌとエロイーズの今生の別れのシーンで繰り返されることになります。肖像画を母親に引き渡し、約束の代金を受け取り、ソフィと固く抱き合って別れを惜しみ合い、荷物をまとめて逃げるように屋敷を出発しようとするマリアンヌの背中に、母親から送られた花嫁衣装を身につけたままのエロイーズが呼びかけるのです。「振り返ってよ」。一瞬だけ振り返り、自分が何度か幻影で見た姿かたちのままの白い衣装のエロイーズの姿を目に収めて、マリアンヌは屋敷を飛び出していきます。
マリアンヌの狼狽ぶりは、詩人として妻を振り返ったというみずからのオルフェの解釈をなぞるにはほど遠いものでした。妻からの呼びかけに応じて振り返った愛の行動なのだというエロイーズの解釈そのままに、エロイーズの必死の呼びかけに答えてしまったものではないかと思います。
point 9 絵を介した一つ目の再会 ★ネタバレ注意
この映画は、絵の教師となったマリアンヌがみずからモデルをつとめながら、若い女性たちにデッサンの指導をしているシーンから始まります(絵画を通して紡がれる「見る・見られる」関係は、この冒頭から逆転するかたちで始まっていたわけです)。生徒の一人が勝手に引き出して教室に飾ってしまった一枚の絵を通して、マリアンヌがエロイーズとの恋を振り返っていくことになります。それは、焚き火の向こうで衣装の裾に火が燃え移った瞬間のエロイーズを描いたものでした。
映画の時間の流れは、エロイーズとのあっけなくも劇的な別れのあと、このマリアンヌの「現在」へと戻ります。そして二度にわたるエロイーズとの「再会」のことが語られます。再会といっても、二人が言葉を交し合うどころか、互いの姿を認め合うことすらできない遠い「再会」です。マリアンヌの側からの一方的な「見る関係」だけの再開なのです。それでいてエロイーズの変わらぬ気持ちが痛いほど伝わってくる、インパクトのあるシーンです。
最初の「再会」は絵画展です。マリアンヌはあいかわらず父の名前を借りて絵を描いています。展覧会にはオルフェが妻を振り返るまさにそのシーンを描いた絵を出品しています。一人の紳士が絵の前に立ち止まり、「オルフェの別れの瞬間を描いた絵は珍しい」とマリアンヌに話しかけます。マリアンヌは実際の作者が自分であることを誇らしげに紳士に伝えます。
その後、マリアンヌは展覧会場に、エロイーズの現在の姿が描かれた肖像画が出されていることに気づきます。白っぽいドレスを着て、小さな娘を傍らに、ふくよかで円満そうな表情をしています。が、よく見るとその手は一冊の本を抱えていて、指が28ページ目に差しはさまれています。28ページというのは、マリアンヌがエロイーズのために自分のヌードを描いてあげた、まさにそのページなのです。マリアンヌは時を超えて、一枚の肖像画を介してエロイーズの変わらぬ思いを知ることになったのです。
ところで、この肖像画が展覧会場に出品されている(売りに出されている?)ということについて、ちょっと気になりました。本来はエロイーズが嫁いだミラノの邸宅に飾られるべき絵画だと思うのですが、それが出品されているということは、エロイーズの結婚に何事かが起こったのかもしれないという気もするのです。このへんはあくまで私の妄想です。
point 10 二つ目の再会とビバルディの音楽 ★ネタバレ注意
二度目の再会は、コンサート会場です。いまだに独り身を守って、たった一人でバルコニー席に座って開演を待つマリアンヌ。その目に、やはりたった一人でやってきたエロイーズの姿が飛び込んできます。向かい側のバルコニー席の一番前に座り、気づいているのか気づいていないのかわかりませんが、一瞥すらもマリアンヌのことを見ようとはしません。
やがてコンサートが開演します。曲はビバルディのヴァイオリン協奏曲「四季」の「夏」の第三楽章です。「四季」のコンサートならふつうは「春」から始めるでしょうし、よしんば「夏」だけ演奏するにしても第三楽章から始めたりするはずはないのですが、これは映画的な演出です。実はこの第三楽章こそはマリアンヌとエロイーズの思い出の曲なのです。
二人が出会って間もないころ、館に置かれていたチェンバロでマリアンヌが記憶を頼りに指でこの曲をたどり、エロイーズに聞かせてやるシーンが出てきます。それまで修道院で教会音楽にしか触れていなかったエロイーズに、世の中にはもっといろいろな音楽があるということを教え諭す場面です(ちなみにこの映画の音楽はこのビバルディ「四季」の「夏」と、島の女たちの歌だけです。ほかにはいっさい音楽は使われません)。
ビバルディの「四季」といえば小学校で習うような曲ですし、とくに出だしの「春」ばかりがいろんなBGMでも使われすぎているので、古めかしくてただただ美しいだけの曲と思われがちですが(少なくとも私は長らくそう思っていました)、一度だけ実際にコンサート会場で全曲演奏を聴いたことがあります。そのときに、それまでなんとなく知っていた音楽の印象とはまったく違って、あまりにも激しく情動的なので動けなくなるくらいに感動したものでした。とりわけ「夏」は、稲妻が光り、雷鳴がとどろき、虫たちが大騒ぎをするという激しい情景をあらわしていて、気持ちが揺さぶられます。
コンサート会場でこの「夏」(三楽章)を聞き入るエロイーズの表情が、映画のラストシーンとなります。激しくかき鳴らされる弦楽器の音の渦の中で、次第に目が潤み、涙がこぼれ、ついには嗚咽するかのように高ぶりを見せていく様子が長回しで捉えられます。でもエロイーズは決して泣き崩れたりはしません。毅然とした美しさを保ったまま、あたかも遠くからマリアンヌが見守っていることを知っているかのように、熱く美しい涙をこぼして見せるのです。
さあ、こうなると、このラストではいったい本当にエロイーズはマリアンヌのことに気づいていたのか、そしてエロイーズの結婚はどうなっていたのか、この先二人が三たびの出会いを果たすことはありうるのかということが無性に気になってきます。
point 11 監督と女優の恋の結末
結論からすると、たとえエロイーズの結婚がそのときには破れてしまっていたのだとしても、マリアンヌは二度とエロイーズと出会うことはなかったと思います。二人の恋は思い出のなかでだけ生き続けるものになっていっただろうということです。
じつは、この映画を製作したセリーヌ・シアマ監督と、エロイーズを演じたアデル・エネルは実際に恋人同士だったそうです。この映画をつくったときには二人の関係はすでに終わっていたのですが、監督はエロイーズの役をアデルを念頭に当て書きし、アデルに新境地を開拓してほしいという願いを込めてフィーチャーしたのだそうです。
「私とアデルは、映画づくりにおけるミューズという概念に終止符を打ちました。演出する側、演じる側、双方の創造性で新たな描き方をしています。私たちはお互いに刺激を与える協力者という関係だったのです」と、シアマ監督はインタビューで語っています。別れてもお互いの才能を信じ合い、こんな共同作業ができるなんて、なんとまあ素敵な関係でしょうか。
というわけで、こんなふうに監督がアデルの新しい旅立ちへの祝福をこめてつくった映画なのですから、ラストシーンのエロイーズの涙にも、きっと中途半端な甘い未来や期待はいっさい含まれていないはずだと思うし、そうであってほしい、それでいいだろうと思うわけです。
ちなみに、この映画の公開当時の、主演二人と監督がいっしょに出ているインタビュー動画などをいくつか見てみました。マリアンヌを演じたノエミ・メルランは黒髪を短髪にし、まるで宝塚の男役のようで、映画で見る以上に端正な女性でした。エロイーズを演じたアデル・エネルは映画で見る以上にカリスマ的で、アーティスティックなニュアンスのある女性でした。二人が並んでいると、その対比的な美しさがあまりにも神々しすぎて、しばらくインタビュー動画を追っかけして見てしまいました。
そして二人とも背がものすごく高いのです。映画のなかでは、ソフィが小柄な女性のように見えていましたが、どうもそうではなく、ノエミとアデルが長身すぎるようです。二人と並ぶとシアマ監督も、やっぱり小さい人に見えてしまうのでした。でも、シアマ監督もとても深く広い知性と慈愛を感じさせる、すばらしい顔の女性だと思います。
とにもかくにもこの映画は、希有な女性たちによる希有な映画だと思います。
私ごとですが
上述したように、この映画の冒頭は「ピアノ・レッスン」へのオマージュを感じさせるのですが、ラストシーンはルカ・グァダニーノ監督の「君の名前で僕を呼んで」を彷彿とさせます。恋に破れて暖炉の火を前に涙ぐむティモシー・シャラメのアップを延々と写した「君の名前で僕を呼んで」と同様に、「燃ゆる女の肖像」のラストシーンはアデル・エネルの名演を引き出した長回しになっています。アデルの泣きっぷりのほうがややウェットですが、恋が破れた痛みと甘美な思い出が交互に襲ってくるかのように、涙が溢れているのにふいに微笑みが浮かんだりする様子も、共通しているように思います。
果たしてこの映画が「君の名前で僕を呼んで」を意識したのかどうか、私の印象が当たっているのか的外れなのかはわかりません。私自身は、よい映画、すぐれた映画は、先人の作品のよいものを参照し、自由に取り込み、オマージュを捧げたりリスペクトを表現するものだと思っていますので、むしろ「そうあってほしい」と思っていますし、この妄想映画館では臆せずにそういうことも言葉にしていきたいと思います。
もうひとつ、「燃ゆる女の肖像」と「君の名前で僕を呼んで」に感じる共通点で私がとくに気に入っているところは、恋人同士となる二人が、互いの知性や感性に礼節をもち敬意をはらっているという点です。二人の恋の「駆け引き」に神話や物語や音楽がつかわれているところも似ています。「君の名前で僕を呼んで」の場合は人物たちの設定がそもそもアカデミックな環境にあるのですが、「燃ゆる女の肖像」は階級を超えて女性たちが友愛を育みあう関係とともに描かれていることから、監督がことさら意図的に女性たちの「知性と感性」を強調して描きたかったのではないかとも思います。
ついでに言うと、お互いの気持ちを知り愛を交換したあとの二人が、いちゃいちゃしながら「いつ恋に落ちたか」ということを確かめ合うシーンも共通しているように思いました。「君の名前で僕を呼んで」では「もっとわかりやすいサインをくれれば、何週間もムダにしないで済んだのに」とエリオがオリヴァーに甘えてすねて見せ、「燃ゆる女の肖像」では、「お互いに仏頂面で時間をムダにしました」とマリアンヌとエロイーズが微笑みあいました。
両方とも美形の男性同士、女性同士の映画で、どのラブシーンも印象的なのですが、この「いつ恋に落ちたか」を確かめ合うシーンは、とりわけ打ち解けた恋人同士の心を許した会話らしくて、大好きなシーンです。知性と感性のあふれる恋人同士だからこそ、こんな他愛もない会話がなんとも愛しく思えるのです(そうでなければ、ただのバカップルの会話になってしまいますね)。
かくして、 「燃ゆる女の肖像」と「君の名前で僕を呼んで」 はいまのところ私が生涯でみたロマンス映画のベストということになります。両方とも男女の恋愛ではなく、女同士、男同士の恋愛が描かれている映画であることは、もちろん私個人の好みもあります。でもそれだけではありません。この二作がLGBT映画といった枠組みを超えて高い評価を得ているようすを見ると、じつはジェンダーにまつわる意識の時代変化にすぐれて敏感な映画であると言えるのではないかと思うのです。こういった映画が普遍的な感動を呼び起こすことで、意識変化の先取りをしていく面もあるに違いないとさえ思います。そういう意味で、私にとってこの二本の映画は、たんなる恋愛映画ではすまないくらい大事な映画なのです。


